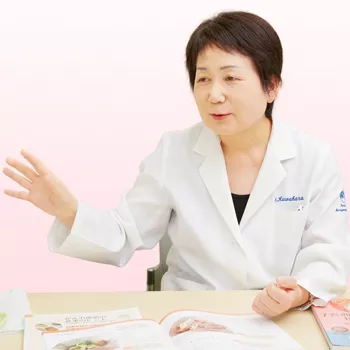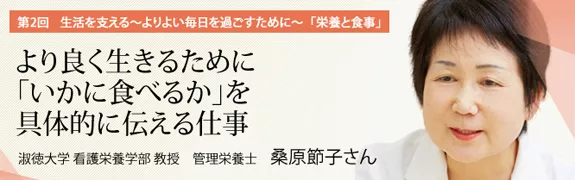
美味しくない理由
抗がん剤治療をはじめとして、がん治療においては副作用が大きな問題になる。嘔気・嘔吐、脱毛、口内炎などはよく知られているが、医療のなかでも見過ごされがちで、かつ一般的にもあまり知られていないのが、食欲不振、味覚障害といった食にまつわる副作用だ。しかし、食は生活の基本であり、人間の体をつくるもの。食にまつわる副作用が、実は治療の妨げになったり、患者さんのQOL(quality of life)を著しく低下させることもある。
現在は淑徳大学看護栄養学部で教鞭を取る管理栄養士の桑原節子さんが、がん患者さんとかかわるようになったのは、1993年、国立がん研究センター中央病院に栄養管理室長として転職したのがきっかけだった。
「それまではいわゆる総合病院に勤めていたのですが、管理栄養士が治療に介入し、栄養指導を行うのは、糖尿病や腎疾患の患者さんがほとんどで、がんの患者さんに携わる機会はありませんでした。」
なぜなら、診療報酬上、「栄養食事指導料」という指導料が算定できる疾患の患者さんが優先されるからだ。もちろん、そうした疾患は栄養管理がより重要だからだが、そのために、そこに当てはまらないがんなどの患者さんにはかかわる機会がほとんどなかったという。
ただ、がんセンターは、当然、がん患者さんばかり。そして入職してすぐに桑原さんが対面したのが、「食事がまずい」という患者さんからの不満だった。
「美味しくないものは出していないはずなのに、患者さんは『なんでこんなまずいものを出すのか』と言うのです。よくよく調べてみると、薬の副作用による食欲不振、味覚の変化、体調の悪さから美味しいと感じられなくなっていたり、生活リズムの違う人と同室で過ごす環境が原因だったりすることがわかってきました。表面上は『食事がまずい』という問題だったのですが、実は、副作用や療養環境が影響していたんです。」