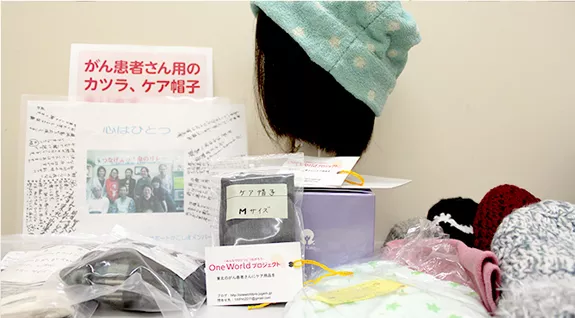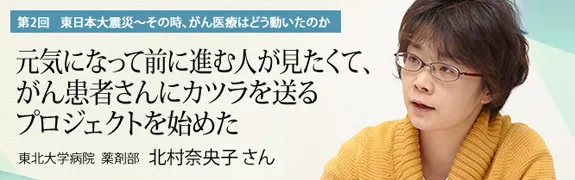
患者さんの命をつなぐ
「まず考えたのは、患者さんの安全を守ること、患者さんの命をつなぐこと」——。
東北大学病院に務める薬剤師の北村奈央子さんは、地震発生のとき、病院の東病棟の4階にいた。化学療法センターで抗がん剤治療を受けている患者さんに薬の説明をし始めたところだった。
持っていた携帯電話に緊急地震速報が入り、アラーム音が鳴り響き、ベッドサイドのテレビからも地震の発生を知らせる警戒音が鳴った。
「嘘じゃないよね?」と思っているうちに、ガガガガガガガガッと揺れがきた。「これはまずい」と思った北村さんは、とっさに目の前の患者さんとその母親の上に覆いかぶさった。
揺れが収まったかと思うと、またすぐにやってくる。断続的な揺れが続くなか、避難経路を確保するために扉を開け、保管している医薬品をチェックした。その日は、月曜日に行う治療のために、400万円相当の抗がん剤が置いてあった。抗がん剤の調剤を行う安全キャビネットが壊れたら困るし、薬などを保管している冷蔵庫が壊れても困る。
「調剤薬局もパニックになっているだろうし、流通もストップするだろう。治療を再開できなくなったら患者さんが困る、患者さんにとって生きる術である薬がなくなったら困る。」そう考えて、いつもなら院外の調剤薬局で出すようにしている薬を、院内での処方に切り替えるよう、医師に頼み込んだ。
特に心配したのが、医療用麻薬だ。抗がん剤治療を受けている患者さんのなかには、医療用麻薬を使って痛みをコントロールしながら、なんとか日常生活を送っている人は多い。もし、なくなれば、あまりの痛みに気を失ったり、「もう生きていけない」と絶望してしまう人もいるだろう。さらに、急に服薬を止めれば、発汗や呼吸困難など禁断症状が起こることもある。
「そうはさせられない。」北村さんは、薬を準備し、一人ひとりの患者さんに手渡した。