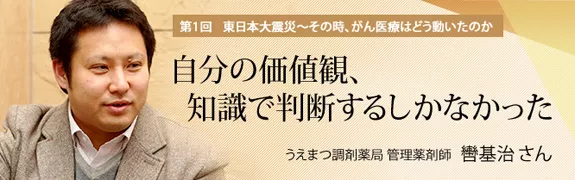
震災直後
カウンターで外をボーっと眺めていたら、どどどどどどどどーっと地鳴りが来て、「来るな、来るな」と思っていたら、ズドンと最初のドカンが来た——。
2011年3月11日14時46分。東日本大震災が起こったとき、薬剤師の轡基治さんは、うえまつ調剤薬局のカウンターの中にいた。前々日から震度4、5の大きな揺れが何度か起きていた。3歳のときに宮城県沖地震を経験し、「いつか大きな地震がくる」と教えられて育ってきた轡さんは、他の宮城県人同様に、どこかで覚悟はしていた。しかし、「ついに来たか」と思いつつも、それは想像以上だった。
普段はどっしりと立っている調剤棚も、調剤用の分包機のような大きな機械も、横に吹っ飛んだ。「中にいたら圧死する。」轡さんは、薬局内にいたスタッフ全員を外に出し、大きな揺れが続くなか、建物の外の金網につかまりながら、携帯電話を取り出し、ツイッターやフェイスブックに「みやぎ、壊滅」「みやぎ、壊滅」と打ち込んだ。

轡さんが勤めるうえまつ調剤薬局は、仙台市の南東、太平洋に面した名取市にある。「田舎の本当に古い集落なので、じっちゃん、ばっちゃんばかりのところ。」薬局の外来で薬を渡すほか、隣にある在宅専門の診療所と協力し、訪問薬剤師として自宅で暮らす患者のもとを回り、薬の管理や飲み方の指導を行っている。
「暗くなる前に職員を家に帰さなければいけない」と、薬局のスタッフを全員家に帰した後、残った診療所のスタッフと一緒に、まず、誰のところに行くべきか、情報の整理を始めた。とはいっても、電子カルテは使えないし、紙カルテは、ガラスが散乱し、足の踏み場もないような診療所の中にある。揺れ続けるなかでなんとか必要な資料を取り出し、人工呼吸器をつけている患者さん、在宅酸素の患者さん、独居の患者さんをピックアップし、「家族が一緒にいるであろう人は申し訳ないけれど後回しにさせてもらって」、気になる患者さんから手分けしてまわることにした。

轡さんが向かったのは、その日の夕方、訪問する予定になっていた寝たきりの独居患者さんだ。山の上に住んでいる患者さんの自宅に行くには、途中、橋を渡らなければいけない。しかし、「暗くなるから、ここから先はダメだ」と、立っていた警官に止められた。その日はやむなく引き返し、翌朝、明るくなってから、遠回りをして橋を通らないルートで行ったところ、家は空っぽ。隣近所の人から「今朝方、救急車が来ていた」と聞いた。冷たくなって亡くなっているところを見つけられ、救急車で運ばれたという。
「精神的にストレスを受けやすい方でした。一人で寝たきりで、古い家のなかで一日中揺られ続けていたのだから、相当ストレスがかかったと思うんです。もし、そばに誰かがいて声をかけてあげられればちょっとは結果が違ったかもしれない。もし自分が行けていたら何かが違ったのかもしれないと思う部分はある。でも、行っていたら、そこに張り付きになって他のことができなかったかもしれないし、たぶん、どうにもならなかったとは思うんですが・・・」と心中を語る。
